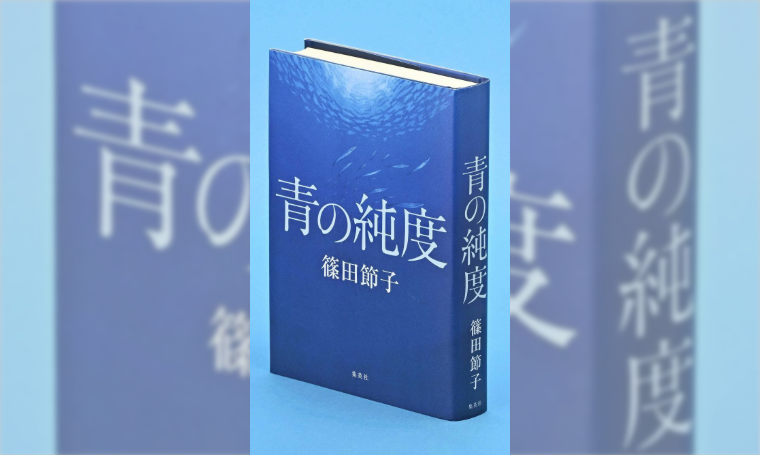
篠田節子さんの小説『青の純度』の書評を執筆しました。共同通信より全国各紙に配信中です。
本書に登場する「マリンアートの巨匠ヴァレーズ」は、バブル期に海中画で大衆の心を掴み、一方で美術界からは黙殺された画家であるとされています。
ある時期からその商法が問題視され、忘れられた画家となっていたヴァレーズ。その作品を商法と切り離して再評価する書籍を著そうとする人物が本書の主人公です。
以上を一読しただけで明らかなように、ヴァレーズのモデルは実在する画家クリスチャン・ラッセンであり、「その作品を商法と切り離して再評価する書籍を著そうとする人物」には、同様の企図のもとラッセンを再評価する書籍を何冊も著してきたぼく(原田裕規)の立ち位置が重ねられます。
しかし本書にはラッセンや拙著の名前は一度も登場せず、巻末の参考文献リストを見ても、拙著にまつわる情報が周到に排除されていました。
この小説は、画家、コーディネーター、ギャラリストなど、アートに携わる人々の倫理観を題材とするものです。しかし本書における著者のふるまいは、書き手としては倫理的とは言い難く、疑問が残るものでした。
たとえば、本書には以下のようなくだりがあります。
インテリア絵画として美術業界には黙殺され、評論家からはけなされるどころかまったく相手にされず、その一方で圧倒的な大衆的知名度を獲得していたヴァレーズ。
──同書、10ページより
これは『ラッセンとは何だったのか?』などの一連の書籍で繰り返し述べられてきた内容に酷似するものです。
バブル期以後、イルカやクジラをモチーフにしたリアリスティックな絵で一世を風靡したクリスチャン・ラッセン。その人気とは裏腹に、美術界ではこれまで一度として有効な分析の機会を与えられずに黙殺されてきた。
──『ラッセンとは何だったのか?』書籍紹介より
また本書では「犯罪的な商法と、作品・作家を切り分け、その販売手法に言及した後、ジャンピエール・ヴァレーズの作品そのものを取り上げ、そこにある芸術と大衆性のせめぎ合いについて語る」ことが必要だという旨が繰り返し説かれています(同、54ページ)。
これも、ぼくが共同で企画した「ラッセン展」や一連の「ラッセン本」の中で繰り返し投げ掛けてきた問題意識と一致するものでした。
さらに本書の主人公は「ヴァレーズ本」を執筆するためにハワイ島へ渡り、ヴァレーズを探して島中を旅するのですが、これもぼくがラッセン本の執筆のためにハワイに渡って行ったリサーチの旅路と酷似する内容でした。
たとえば本書の中でヴァレーズは、ハワイを襲ったハリケーンによって自宅が被災して作品が失われてしまったという描写があります。この出来事は、ヴァレーズの生死自体への疑問が生まれるきっかけになったという意味で、この物語における転換点になっています。
災害による画家の安否の不安──これは、2023年にラッセンの故郷ラハイナを山火事が襲い、ラハイナの町は全焼、100名以上の死者を出しながら、ラッセン自身の名前も一時期は行方不明者リストに掲載されていたという事実を彷彿とさせるものです。
この事実はニュースなどで報道されたものではなく、当時ぼくがマウイ郡の発出した行方不明者リストを入手し、Xに投稿したことによって明るみに出た内容でした(2023年8月15日の投稿)。
この件に関しては、日本語・英語ともにメディア等で報道された事実は確認できず、現在でも公の場で発信された情報としては、ぼくのXの投稿がほとんど唯一の情報源となっています。しかしやはり、そのことに対する言及もありませんでした。
そして本書の主人公は「ヴァレーズを実直に再評価する本」を書くためにハワイを取材し、その過程で知り合ったハワイの日系人と以下のような会話をするくだりがあります。
「すべての墓石が西の海側を向いて建てられているのです。海を隔てた日本を向いているのです」
ぼく自身も「ラッセンを実直に再評価する本」を書くためにハワイに渡り、現地の日系人と交流していたのですが、その際にやはり「ハワイの日系人の墓石はすべて西の方角を向いて建っている」ということを現地の仏教関係者に教えてもらったことがありました。
このことは、サブタイトルに「ラッセン」の名前が入った拙著『とるにたらない美術:ラッセン、心霊写真、レンダリング・ポルノ』における「ラッセン論」とは別の論考(「アンリアルな風景」「ハワイ紀行」など)で記していた内容です。
これらのテキストは3DCGの表現史や日系人の歩みに関するものであり、ラッセンとはほとんど無関係な内容ですが、そうしたテキストさえも参照されたと思しき内容が含まれており驚きました。
……と、このように記述の手続きにおいては幾つもの疑問が残る内容でしたが、アートの価値決定のプロセスに対する疑問や、アートにおける作者の記名性の問題をサスペンスに仕立てる手腕は見事なもので、爽快な読後感のある物語になっていました。
だからこそ、願わくば適切な手続きのもとで記されてほしいものと思いました。
ラッセンにまつわるリサーチは、ぼくが10数年の年月をかけて、ハワイへの自費での渡航も経ながら行ってきたものです。取材のために費やした時間もコストも莫大なものでした。
本書の物語は、そうして得た知見や情報にあまりに多くの部分で立脚しているように思われました。いやむしろ、それらが物語を構成する基本的なアイデアになっているからこそ、読者が拙著にはたどり着けないように、敢えて参考文献リストから情報を除外したのではないかと邪推したくなるほどのものでした。
実際に本書のレビューを確認しても、筆者の「リサーチ力」や「斬新なアイデア」に対する賞賛のコメントが数多く寄せられている一方で、その参照源と思われる拙著の存在について指摘するコメントは確認できませんでした。
一方は直木賞なども受賞しているベストセラー作家であり、他方は発行部数で一桁以下も劣るマイナージャンルの書き手であるというこの権力勾配の中で、この状況は搾取的であるように感じられてしまいました。
もちろん、以上の指摘は状況証拠から見た推測に過ぎず、著者の真意は測りかねるものですが、ラッセンに関する一連の書籍(『ラッセンとは何だったのか?』『とるにたらない美術』『評伝クリスチャン・ラッセン』『ラッセンとは何だったのか?増補改訂版』)を著してきた当事者としては、どうしても見過ごすことはできず、指摘させていただきました。
ただ繰り返しますが、小説として本書は十分にスリリングで、優れた作品になっています。
書評と合わせてぜひ『青の純度』や『ラッセンとは何だったのか?』をご一読いただけますと幸いです。
info:
篠田節子『青の純度』書評(評者:原田裕規)
共同通信配信(全国各紙)
【BOOK】絵画の疑念、物語に昇華 「青の純度」篠田節子著(静岡新聞DIGITAL)
[読書]小説 青の純度 篠田節子著 忘れられた画家を求めて(沖縄タイムス)
書評 小説 青の純度(篠田節子著)(山陰中央新報デジタル)
関連リンク
編著『ラッセンとは何だったのか?』(フィルムアート社、2013年)
単著『とるにたらない美術 ラッセン、心霊写真、レンダリング・ポルノ』(ケンエレブックス、2023年)
単著『評伝クリスチャン・ラッセン 日本に愛された画家』(中央公論新社、2023年)
編著『ラッセンとは何だったのか?[増補改訂版]』(フィルムアート社、2024年)